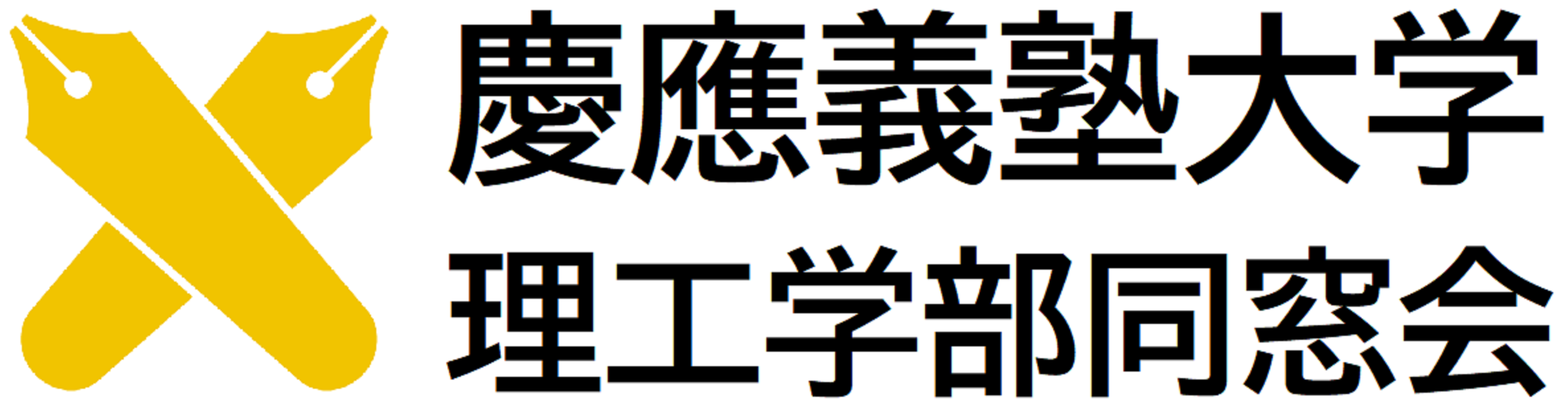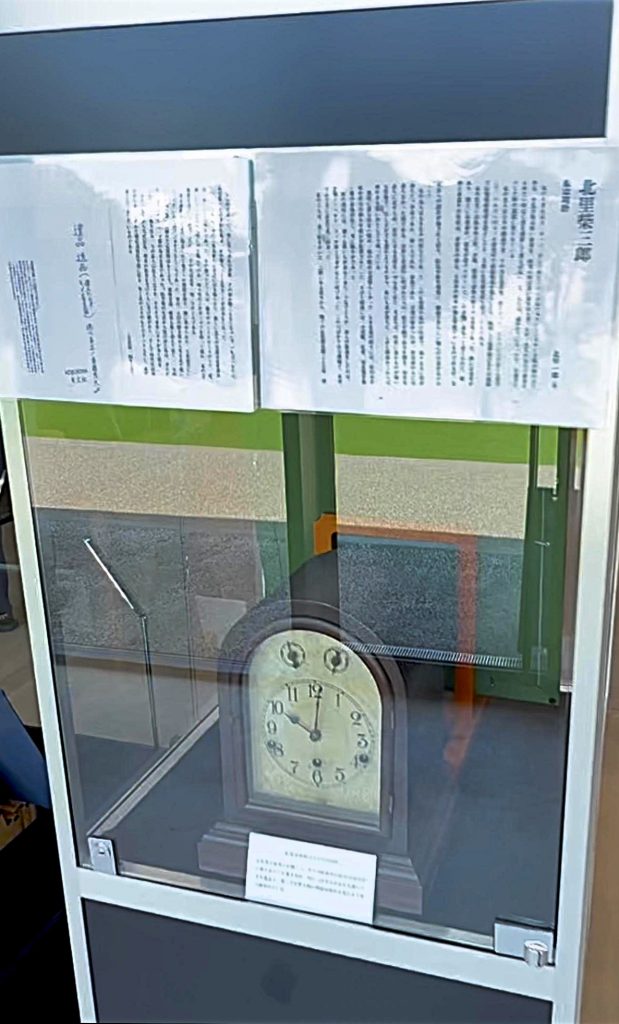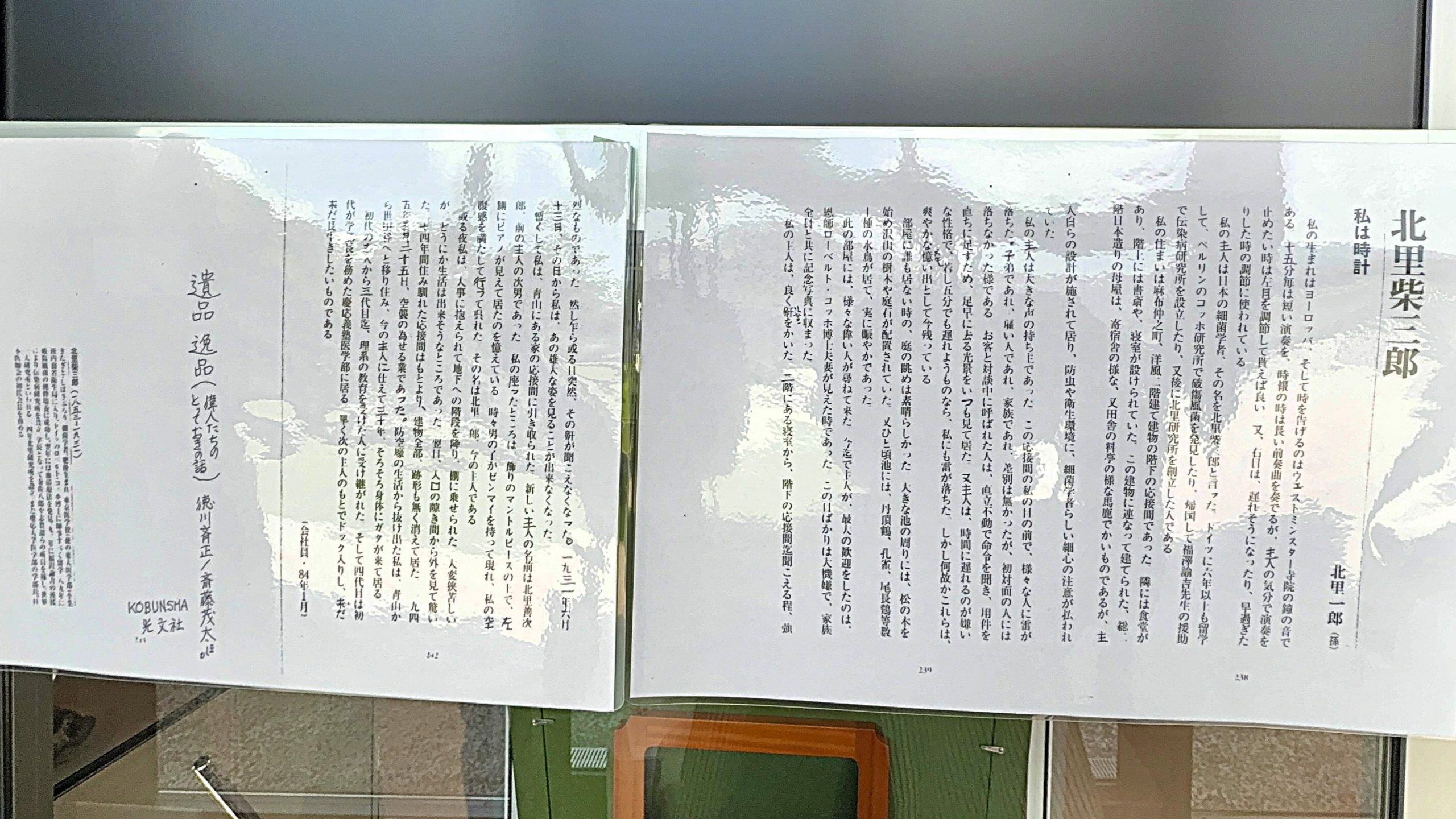『私は時計』故 北里一郎君著(北里柴三郎記念館 展示品)
先日、訪れた 北里柴三郎記念館 にて拝見した展示品をご紹介させていただきます。故 北里一郎君が執筆した『私は時計』と、そこに登場する主人公の時計です。北里一郎君は、慶應義塾の元評議員であり、理工学部同窓会の元会長でした。永年にわたり慶應義塾ならびに理工学部同窓会を支えていただき、お亡くなりになるまで当会の名誉顧問を務めてくださいました。
ご子息の北里英郎君は、北里大学 名誉教授で北里柴三郎記念館 名誉館長であり、今年10月19日開催の理工学部同窓会 総会・特別講演会にて講演講師を務めてくださいます。先日の事前収録の際、我々のために、こちらの展示品をご用意してくださいました。
北里柴三郎
『私は時計』北里一郎(孫)
私の生まれはヨーロッパ、そして時を告げるのはウエストミンスター寺院の鐘の音で
ある。十五分毎は短い演奏を、時報の時は長い前奏曲を奏でるが、主人の気分で演奏を
止めたい時は左目を調節して貰えば良い。又、右目は、遅れそうになったり、早過ぎた
りした時の調節に使われている。私の主人は日本の細菌学者、その名を北里柴三郎と言った。ドイツに六年以上も留学
して、ベルリンのコッホ研究所で破傷風菌を発見したり、帰国して福澤諭吉先生の援助
で伝染病研究所を設立したり、又後に北里研究所を創立した人である。私の住まいは麻布仲之町、洋風二階建て建物の階下の応援間であった。隣には食堂が
あり、階上には書斎や、寝室が設けられていた。この建物に連なって建てられた、総二
階日本造りの母屋は、寄宿舎の様な、又田舎の料亭の様な馬鹿でかいものであるが、主
人自らの設計が施されて居り、防虫や衛生環境に、細菌学者らしい細心の注意が払われ
ていた。私の主人は大きな声の持ち主であった。この応接間の私の目の前で、様々な人に雷が
落ちた。子弟であれ、雇い人であれ、家族であれ、差別は無かったが、初対面の人には
落ちなかった様である。お客と対談中に呼ばれた人は、直立不動で命令を聞き、用件を
直ちに足すため、足早に去る光景をいつも見て居た。又主人は、時間に遅れるのが嫌い
な性格で、若し五分でも遅れようものなら、私にも雷が落ちた。しかし何故かこれらは、
爽やかな憶い出として今残っている。部屋に誰も居ない時の、庭の眺めは素晴らしかった。大きな池の周りには、松の木を
始め沢山の樹木や庭石が配置されていた。又ひと頃池には、丹頂鶴、孔雀、尾長鶴等数
十種の水鳥が居て、実に賑やかであった。此の部屋には、様々な偉い人が尋ねて来た。今迄で主人が、最大の歓迎をしたのは、
恩師ローベルト・コッホ博士夫妻が見えた時であった。この日ばかりは大機嫌で、家族
全員と共に記念写真に収まった。私の主人は、良く鼾をかいた。二階にある寝室から、階下の応接間迄聞こえる程、強
烈なものであった。然し乍ら或る日突然、その鼾が聞こえなくなった。一九三一年六月
十三日、その日から私は、あの雄大な姿を見ることか出来なくなった。暫くして私は、青山にある家の応接間に引き取られた。新しい主人の名前は北里善次
郎、前の主人の次男であった。私の座ったところは、飾りのマントルピースの上で、左
側にピアノが見えて居たのを憶えている。時々男の子がゼンマイを持って現れ、私の空
腹感を満たして行って呉れた。その名は北里一郎、今の主人である。或る夜私は、大事に抱えられて地下への階段を降り、棚に乗せられた。大変狭苦しい
が、どうにか生活は出来そうなところであった。翌日、入口の隙き間から外を見て驚い
た。十四年間住み馴れた応接間はもとより、建物全部、跡形も無く消えて居た。一九四
五年五月二十五日、空襲の為せる業であった。防空壕の生活から抜け出た私は、青山か
ら世田谷へと移り住み、今の主人に仕えて三十年、そろそろ身体にガタが来て居る。初代の主人から三代目迄、理系の教育を受けた人に受け継がれた。そして四代目は初
代が学部長を務めた慶応義塾医学部に居る。早く次の主人のもとでドック入りし、未だ
未だ長生きしたいものである。(会社員・84年1月)
遺品逸品(偉人たちのとっておきの話)徳川斉正/斎藤茂太ほか
KOBUNSHA 光文社