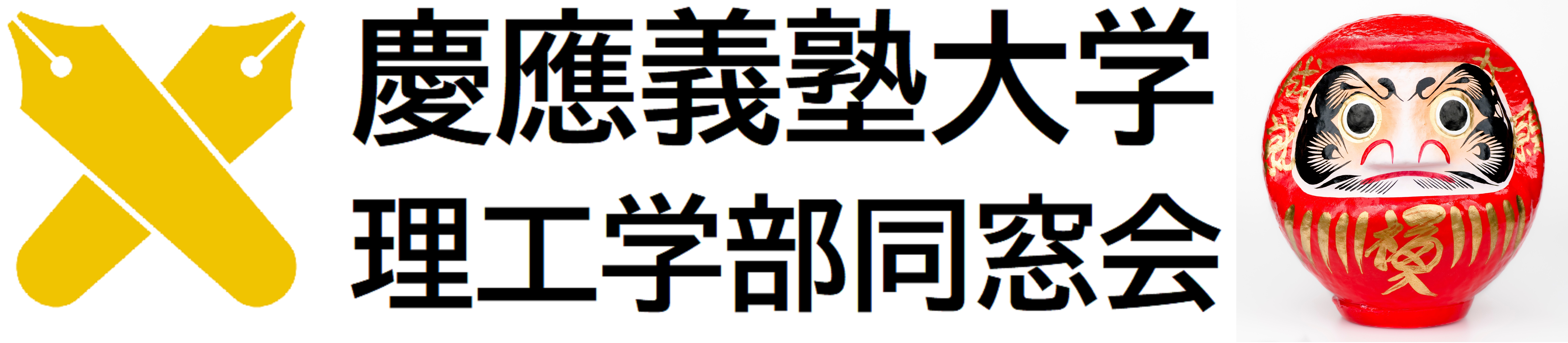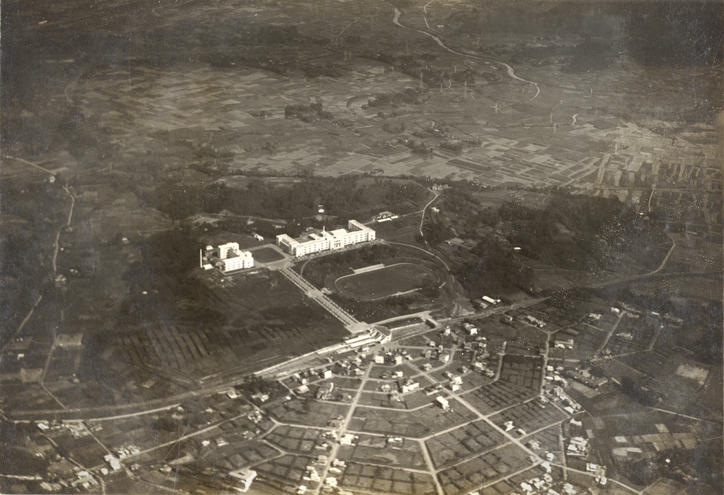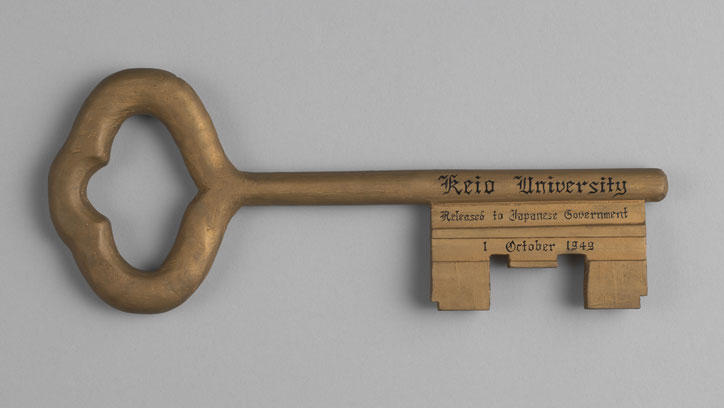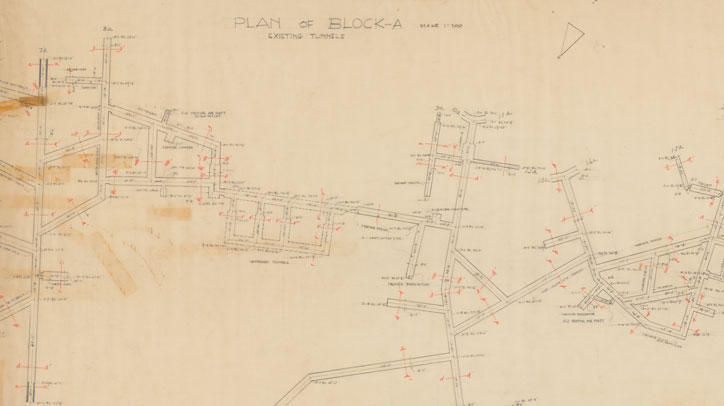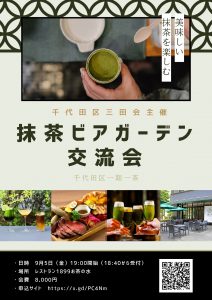終戦80年・慶應義塾と戦争
慶應義塾が発行する広報誌『塾』(年4回発行)に掲載された記事、「終戦80年・慶應義塾と戦争」をご紹介させていただきます。
三田・信濃町キャンパス編と日吉キャンパス編の二部作となっております。
(引用元:https://www.keio.ac.jp/ja/keio-times/features/2025/6/、https://www.keio.ac.jp/ja/keio-times/features/2025/8/)
三田・信濃町キャンパス編
2025年は、太平洋戦争終結から80年となる節目の年。慶應義塾のキャンパスはこの戦争において全国の大学の中でも最大の空襲被害に遭った。また、約3500名もの塾生を学徒出陣で戦地に送り出し、2200名以上の慶應義塾関係者が戦没している。今号では三田・信濃町両キャンパスにおける戦争による被害と戦後の復興の痕跡をたどりたい。
空襲で焼け落ちた図書館旧館 (東方社撮影 東京大空襲・戦災資料センター蔵)三田キャンパスの復興は
義塾のシンボル図書館旧館から1945(昭和20)年5月24日未明〜25日、そして26日の2回にわたる米軍爆撃機による空襲で、三田キャンパスでは木造校舎のほとんどが焼失。塾監局や三田演説館などは焼け残ったが、慶應義塾のシンボルである煉瓦造りの図書館旧館は本館部分の閲覧室と事務室、そしてステンドグラスなどが失われた。被災に備え周囲の木造建築物を撤去していたことや、教職員や学生による懸命の消火活動により書庫は延焼を免れ、多くの貴重文献も疎開させており無事であったが、空襲の爪痕は大きかった。
戦後、1947(昭和22)年の創立90年記念式典において、創立100年に向け10年間を期した復興への決意が掲げられると、まず着手されたのは図書館旧館の修復だった。1949(昭和24)年5月に工事は完了。この時点では透明なガラスが入っている状態だったステンドグラスも、1974(昭和49)年に復元された。
慶應義塾の戦後復興の象徴ともなった図書館旧館は、その後も増改築や改修工事を重ね、重要文化財としてその姿を今に伝えている。
塾内の美術品が伝える
戦災の記憶と復興への意志
あえて戦災の痕跡を残し修復された現在の「手古奈」三田キャンパスには、戦争の記録を歴史的事実として後世に伝え、戦没者への鎮魂や平和への思いを込めた数々の美術品が建立されている。図書館旧館1階に置かれた「手古奈」は『万葉集』で詠まれた悲劇の女性をモチーフに彫刻家・北村四海(しかい)が手掛けた大理石彫刻(1909年頃)。空襲によって両腕部分を失うなど大きく破損したが、2009(平成21)年、60余年ぶりに公開された。事前の修復作業にあたっては、戦争という歴史的事実を風化させないよう、焼夷弾の煤をあえて完全に洗浄しない方法がとられた。
塾監局前庭園に建立された「平和来(へいわきたる)」(1952年・朝倉文夫)は、慶應義塾関係の戦没者追悼のため、「昭和7年三田会」の卒業25年記念として寄贈されたもの。台座には、戦時中の塾長だった小泉信三による碑文「丘の上の平和なる日々に 征きて還らぬ人々を思ふ」が刻まれている。1998(平成10)年には、「還らざる学友(とも)の碑」を建立。台座には、2014(平成26)年に慶應義塾関係戦没者名簿が納められた。また、メディアセンター地下1階には、戦没学生慰霊像「わだつみのこえ」(1950年・本郷新)がある。
1949(昭和24)年に完成した「学生ホール」。その中に設けられた学生食堂の東西両壁面には、戦後民主主義の到来で伸びやかに歌い語らう青年男女たちを描いた猪熊弦一郎の壁画「デモクラシー」が飾られた。本作はホール取り壊し後は西校舎内生協食堂に移設され、現在も学生たちを見守っている。上部が三角形となっているのは学生ホール時代の屋根の形の名残である。
西校舎内生協食堂の東側の壁面に移設された現在の「デモクラシー」
西校舎内生協食堂の西側の壁面に移設された現在の「デモクラシー」信濃町キャンパスの戦災と
関係者たちの奮闘の痕跡信濃町キャンパスは1945(昭和20)年5月24日未明からの空襲で罹災し、全体の約6割を焼失するという甚大な損害を受けた。焼け残った予防医学校舎敷地内には今も六角形の焼夷弾の痕が残っている。
焼夷弾が降り注ぐ中、教職員と学生による特設防護団の懸命の努力もあって、鉄筋コンクリートの建造物は罹災を免れ、入院患者約180名を一人の負傷者も出さず無事退避させることができた。その奮闘ぶりは翌25日付の朝日新聞で「挺身隊八十名、看護婦二百七十名は屋上の焼夷弾を手づかみで投げ捨てるもの、あらゆる容器を利用して水をかけるもの、若い人達は懸命に消した」と報道された。そしてこれほどの被害を受けながらも、被災後間もなく臨床部門を残存建物に移して診療が再開されたのである。
空襲で多くの建物が焼失した信濃町キャンパス(福澤研究センター提供)大学病院敷地内の一角にある「食研跡地記念の碑」。空襲に耐えた食養研究所(食研)には臨床の各教室が移転し、研究室として利用された。戦後の厳しい条件の中で各科が共に研究した場として長く医学部関係者に親しまれていたが、1990(平成2)年に建物が解体されるにあたって、外壁の一部が残されるとともに記念碑が建立された。
また、かつて大学病院には病棟間をつなぐ「西病舎在来病棟連絡用地下道」という長さ23メートルの地下通路があった。空襲時に患者を本館から別館へ避難させる際には、この地下道が使われた。現在この地下通路は病院内の電気配管を通すパイプスペースとして利用されている。
多くのものが失われた戦争の終結から80年。キャンパスに刻まれた教育と研究、医療の灯を守り抜こうとした人々の努力、そして戦争の記憶と平和への祈りに目を向け、希望と平和に満ちた未来を切り開いていってもらいたい。
この記事は、『塾』 SPRING 2025(No.326)の「ステンドグラス」に掲載したものです。
日吉キャンパス編
前回(春号)の三田・信濃町両キャンパスに続き、今号では日吉キャンパスを取り上げる。戦争末期、日吉の校舎の一部は帝国海軍に接収され、地下には連合艦隊司令部などが建設された。そして敗戦後、今度は日本に進駐した米軍によっておよそ4年間にわたって接収される。キャンパスと戦争との関わり、そしてその痕跡である「日吉台地下壕」について紹介する。
竣工時の日吉キャンパス(福澤研究センター提供)田園都市構想に沿った
「日吉キャンパス」誕生昭和を迎えた頃、学生数の増加により慶應義塾では三田キャンパスが次第に手狭になり、1927(昭和2)年より新キャンパス開設を検討し始める。すると沿線の田園都市構想の一環として学校誘致による旅客需要増を目指す東京横浜電鉄株式会社(現・東急電鉄株式会社)から“日吉台”の土地約7万2000坪を無償提供するとの申し出があり、日吉キャンパスの開設が決まった。
1934(昭和9)年4月に大学予科の移転をもって日吉キャンパスの歴史が始まる。同年11月には福澤諭吉誕生100年を兼ね、日吉開校記念祝賀会が開催された。1939(昭和14)年には、工学部(現・理工学部)の前身である「藤原工業大学」が開校。同大学は1944(昭和19)年に慶應義塾に寄付された。
日吉開校記念祝賀会(福澤研究センター提供)戦争に翻弄され続けた
日吉キャンパスの歩みしかし、その頃第2次世界大戦の戦況は悪化の一途をたどり、1943(昭和18)年10月には満20歳に達した文系学生の徴兵猶予が廃止され、終戦までの間、約3500名の塾生が学徒出陣により戦地に送られた。
また当時の文部省は校舎の貸与を慶應義塾に求め、日吉キャンパスでは1944(昭和19)年3月から第一校舎や寄宿舎などを海軍省に貸与することになった。日吉は地理的に霞が関(海軍省・軍令部)と横須賀(軍港)のほぼ中間に位置し、無線通信環境も良好。しかもキャンパスの寄宿舎は鉄筋コンクリートの堅固な建物で、個室も多く司令部機能はもちろん、居住環境としても最適と考えられたのだ。
まず海軍による寄宿舎の全面使用が始まり、同時期にキャンパス地下で軍事施設の建設が急ピッチで進んだ。建設された施設は軍令部第三部退避壕、連合艦隊司令部地下壕、航空本部等地下壕、人事局地下壕で、総延長距離は約2.6㎞に及ぶ。キャンパス外部には艦政本部地下壕も作られ、これらをまとめて「日吉台地下壕」と呼ぶ。
1945(昭和20)年4月、日吉キャンパスは空襲によって工学部校舎の約8割が焼失した。同年8月14 日に日本は連合国軍に無条件降伏を決定。米軍が最初に日吉キャンパスに足を踏み入れたのは東京湾上の戦艦ミズーリで行われた降伏文書調印の2日後の9月4日と言われている。同8日には「日吉軍事占領の命令書」が渡され、米軍による日吉キャンパス接収が始まった。
キャンパスの返還式で手渡された木製の大鍵(福澤研究センター提供)接収直後から当時の渉外室や塾員有志の三田リエーゾンクラブによる米軍への度重なる返還交渉、さらに当時の学生新聞『三田新聞』でほぼ毎号キャンパス返還に関する特集記事が組まれた。こうした慶應義塾一丸となった返還への取り組みがようやく実を結び、1949(昭和24)年、米ソ対立による占領政策の転換を背景に、6月27日に接収解除が決定。同年10月1日の返還式では、返還のシンボルとして米軍より金色木製の“大鍵”が当時の潮田江次塾長に手渡された。
今も残る「日吉台地下壕」は
平和への思いを巡らす拠点戦後復興の中で、「日吉台地下壕」の存在は長く忘れ去られていた。まずその存在に注目したのは中高生たちだった。最も古い記録では1958(昭和33)年の慶應義塾普通部生徒が労作展の展示で取り上げ、11年後の1969(昭和44)年には慶應義塾高等学校の文化祭「日吉祭」で生徒有志が研究発表を行い、その成果は後に小冊子『わが足の下』にまとめられた。それによると「高校に入学して校舎の裏の谷に地下壕の入り口があるのを発見した。(中略)内部の様子を詳しく知るために、自分たちで地図を作りながら歩き回った」とある。生徒たちは入坑許可を得て内部を探索・測量するだけでは飽き足らず、当時を知る関係者への聞き取りも行っている。本格的な調査・研究が始まったのは80年代半ばのことだったが、当時最も有力な資料となったのは高校生の調査記録『わが足の下』だった。今世紀に入ると考古学による学術調査も始まり、戦争や平和について考える拠点として現在も研究が続けられている。
大学に残る最古の地下壕の測量図(福澤研究センター提供)日吉キャンパスの地下に、80年前の戦争の痕跡「日吉台地下壕」が今も存在している。そのことから目を背けるのではなく、今から56年前に知的好奇心によって調査研究に取り組んだ中高生たちの営為は、まさに学びの原点と言える。塾生は、自分たちの「足の下」にも目を向けつつ、自由に学び、研究できることの意味を心に刻みながら、日々の活動に取り組んでもらいたい。
地下壕入口
現在の地下壕内作戦室跡。左は暗号室・電信室への通路◆参考映像◆
【あの日、あの時、映像でよみがえる慶應義塾】~「VIRIBUS UNITIS 力を合せて-慶應義塾復興記録1947~1949-」(10分44秒)この記事は、『塾』 SUMMER 2025(No.327)の「ステンドグラス」に掲載したものです。