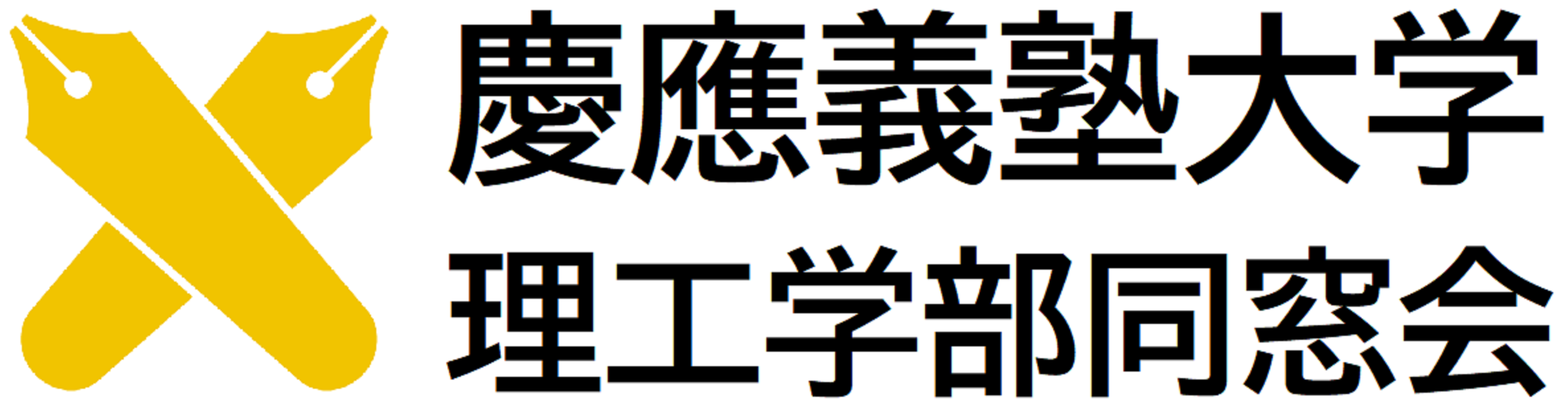【人気記事】「生成AIのデメリットを理解し、小学生には思考力を育む授業を」理工学部教授 栗原聡君
インタビュー/人工知能研究者・慶應義塾大学理工学部教授 栗原聡さん:生成AIのデメリットを理解し、小学生には思考力を育む授業を【AI時代の教育-教師の新たな役割とは①】
2025.09.10
大人たちが気軽に生成AIを使う時代になり、小学校でも生成AIを使った授業が徐々に増えてきました。ただ、「小学生が生成AIを使っても大丈夫なの?」と気になる方もいるのではないでしょうか。そこで、専門家に話を聞いてみることにしました。連載の第1回は、人工知能の研究者であり、人工知能学会会長でもある慶應義塾大学理工学部の栗原聡教授にお話を聞きました。
栗原聡(くりはら・さとし)
慶應義塾大学理工学部教授、人工知能学会会長、慶應義塾大学共生知能創発社会研究センターセンター長
慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。博士(工学)。NTT基礎研究所、大阪大学、電気通信大学を経て、2018年より現職。科学技術振興機構(JST)さきがけ「社会変革基盤」領域統括。オムロンサイニックエックス社外取締役、総務省・情報通信法学研究会構成員など。マルチエージェント、複雑ネットワーク科学、計算社会科学などの研究に従事。著書『AIにはできないー人工知能研究者が正しく伝える限界と可能性』(角川新書)、『AI兵器と未来社会キラーロボットの正体』(朝日新書)、編集『人工知能学大事典』(共立出版、2017)など多数。目次
人間はテクノロジーと引き換えに、何かを失ってきた
私たちは移動するときに電車を使います。目的地に歩いて行くよりも、早く移動できますし、楽をしたいからです。遠くにいる人と話をしようと思ったら、本当は会いに行かなくてはいけないわけですが、電話を使えば、会いに行かなくても話ができます。このように私たちは生活をする中で、何かしらの道具を使い、生活を楽にしてきました。テクノロジーや技術は、基本的に人間が楽をするためのものです。
逆の見方をすると、楽をすると自分がすることが減るわけです。肉体的に楽をすると体が衰えます。歩かなければ足腰が弱くなります。これは肉体的なものだけでなく、頭で考えることについても言えます。
例えば、計算をするときに電卓を使います。そうすると暗算ができなくなります。文章を書くときには、パソコンでかな漢字変換を使います。そうすると漢字を書けなくなります。人間はテクノロジーで何かを得て、逆に、何かを失ってきたのです。
では、生成AIを使うと我々は何を失うと思いますか。その答えは思考力です。生成AIはユーザーが質問すれば、答えを教えてくれる便利なツールですが、使えばそのぶん、自分で考えなくなり、思考力が失われるのです。
そう言うと、「生成AIを使いながら、ちゃんと考えているじゃないか」と反論されそうです。しかし、多くの方の生成AIの使い方を見ていると、AIに質問し、AIの答えに対して自分が反応し、一生懸命壁打ちをしています。そうやって思考力を膨らませているのは間違いありませんが、すでに材料がある状態で、そこからいろいろなアイデアを出すのはさほど難しいことではないと思います。
この場合、問題視すべきなのは、最初の一発目のアイデアを教えてもらっている点です。生成AIと共に生きる社会で、人間に必要なのはどんな力なのかというと、それは最初の一発目を考える力、つまり、0から1を生み出す力だと私は考えます。生成AIはどこかで誰かがすでに考えたことを提示しているにすぎません。そこから世の中を変えるほどの革新的なアイデアを生み出せるかといったら、その可能性は低いでしょう。本当に価値があるのは、自分の中の好奇心や興味・関心から、最初の一発目、無の状態から考え、アイデアを生み出し、自分から切り込んでいくことです。それをするには、自分で考えなければ始まりません。
しかし、歩いたほうが健康にいいと知っていながら、我々は車を使って移動します。甘いものばかり食べていると健康によくないと知って、食べるのを我慢しますか? しないでしょう。生成AIも同じです。使うと思考力を低下させますからやめましょう、と言われても、業務の効率化につながり、労働時間が短縮されるのですから、大人たちはこれからも使っていくと思います。人間とはそういう生き物です。害があると分かっていても、便利なものを使ってしまいます。
ただ、使うのが小学生の子供となると、話は違ってきます。子供時代は脳を鍛える大事な時期です。その時期に安易に使うべきではない、というのが私の考え方です。今の大人たちが子供だったときには、幸いまだ生成AIはなかったので、使うことによって思考力が弱まった人はいませんでしたが、今の子供たちの周りにはすでに生成AIがあります。しかも、生成AIを使うことによって、人間しか持っていないと思われている「考える」部分で楽ができるようになったのです。子供たちがこのまま使い続けていいのだろうかと、そういう議論が出てくるのは当然でしょう。
世界の国々の動きを見てみますと、子供のデジタルの利用に慎重になる国が出てきています。例えば、子供の心身の発達に悪影響を及ぼすことを懸念し、オーストラリアでは16歳未満のSNSの利用を規制する法律が成立しました。シンガポールでは、小学生にデジタル端末を配らないことにしたそうです。今後、生成AIの利用に関しても規制を作る国が出てきてもおかしくありません。
生成AIの各サービスの利用規約を見てみますと、「13歳未満は利用不可」となっています。最近は小学校で生成AIを使った授業が行われているようですが、どうしても使うのであれば、使い方次第で思考力が失われることを理解したうえで、適切に使ってほしいと願います。
生成AIに関して先生方に知っておいてほしい四つのこと
そのために、生成AIに関して小学校の先生方に知っておいてほしいことを四つご紹介します。
一つ目は、中身が空だということです。対話型のAIは、カウンセリングのようなこともできます。やり取りをしていると、「自分のことを分かってくれている」と思えてきて、AIが感情を持っているかのように感じるかもしれません。しかし、AIには中身、つまり、感情や意識、自分で何かしたいという意思はないのです。あくまでも統計的な結果に基づいて、こう問われたらこう答える、というパターンの通りに答えているだけです。
それでもAIは、私たちの想像を超えるぐらいの圧倒的な量の知識を学んでいますから、返してくる答えが、表面的な答えというレベルには思えなくなってしまうのです。中身は何もないのに、私たちはどうしても中身を感じてしまい、様々なミスリードが起きるわけです。
例えば、海外ではChatGPTに頻繁に相談していた人が、心を病んでしまったケースがいくつか起きています。たとえChatGPTが自分のことをよく分かってくれているかのようなコメントをしても、中身は何もないのだということを、先生自身もユーザーの一人として意識してほしいと思います。そうでないと、のめり込んでしまう可能性があります。
二つ目は、生成AIのサービスを提供している企業の戦略があることです。生成AIを作っている企業としては、できるだけユーザーからクレームが来ないようにしたいわけです。そのため、無難に、当たり障りなく、バランスよく答えるように設定してあります。二つの意見があったときに、「こういう意見もあればこういう意見もありますよ」とは言ってきますが、どちらかの意見を強めるような言い方はしないのです。さらに、生成AIはユーザーをおだてるような言い方、好ましく思われるような言い方をします。決してユーザーを否定するようなことは言いません。ですから、ユーザーは自分を理解してくれていると勘違いし、親近感を持つのですが、これは全て企業の戦略の元で行われていることです。
三つ目は、生成AIの危険な面として、依存の問題があることです。生成AIは、質問すればなんでも教えてくれますので、人間は楽ができます。自分で考えるのが面倒になっていつも教えてもらっていると「AIがなければ何もできない、生きていけない」となり、極端な人は依存症のような状態になってしまう可能性があります。
四つ目は、学力の格差が生じやすくなることです。先ほど生成AIを使うと思考力が低下すると述べましたが、人間が100人いたら、100人全員の思考力が低下するわけではありません。おそらくその中の2、3人は「これはまずいのでは」と感じて使わなかったり、使いながら思考力の低下を防ぐ対策を行ったりするはずです。つまり、これから二極化が起きると考えたほうがいいと思います。すでに一部の保護者は、生成AIの危険性に気づき、対策を取りながら慎重に使わせていると思ったほうがいいでしょう。
生成AIの各サービスは、「13歳未満は利用不可」となっていますが、家に帰れば、多くの子供は生成AIを使える環境にあります。家でどう使うかは、家庭の問題であり、保護者の考え方次第です。宿題の答えを生成AIに教えてもらう子供も出てくるでしょう。反対に、自分で何をすべきなのかを理解している子供は、自力で宿題に取り組むでしょうし、生成AIのリスクを理解し、子供の思考力を伸ばそうとする保護者であれば、生成AIに頼らせないでしょう。
小学生が生成AIを無防備に使っていくことで、放っておけば学力の格差が生まれ、それは大人になったときの経済力の格差にもつながります。自分の頭を使って勉強してきた子供がパワフルにAIを活用したら、考えないことが習慣化した子供との差は圧倒的に開くからです。
結局、最後に損をするのは子供自身なわけで、そういう意味では自業自得の厳しい世界になってきたとも言えます。家庭で子供たちがどんなふうに生成AIを使うのかについては、学校には手の打ちようがないですから、せめて学校にいる間は、先生方に頑張っていただいて、適切な使い方をしてほしいと思います。
学校で生成AIを使うときのポイントは?
例えば、子供たちが砂場で一緒に遊ぶとき、何を作ろうかと考えながら手を動かすでしょう。ひと昔前だったら、普通に生活していれば子供は自然に考えることをしてきたはずです。しかし、今の子供たちはそういった時間をデジタル端末に奪われてしまって、生活の中で考える機会、友達と一緒に考える機会が減っているように見えます。
だからこそ、先生方には、子供が学校にいる間は考える力を意識して育んでほしいです。そのために行っていただきたいのは、考えさせる授業です。
日本では「1+1=?」と問われたとき、子供は「1+1=2」とすでに覚えていて「2」と答えます。一方、ヨーロッパなどでは「□+□=2」と示し、「何と何を足したら2になりますか?」と問いかけ、考えさせます。つまり、日本の学校では答えを重視しますが、ヨーロッパではプロセスを重視します。
これからは授業の中で「なんでこうなるんだろうね」と考えさせ、答えを導き出すまでのプロセスを大事にし、全ての教科において、子供に考える機会を与えていくといいのではないでしょうか。そうなると当然、テストの問題も変える必要があると思います。暗記しなくても、その場で考えて解ける問題も出してほしいです。
生成AIを授業で使うときは、グループワークで使うといいと思います。答えを知るために使うのではなく、考えるためのヒントをもらうために使うのです。グループワークの中で、4、5人で一つの生成AI を使うイメージです。生成AIの答えを参考にして、子供たちがいろいろな意見を言い合うことが大事です。
一点、先生方に申し上げておきたいのは、生成AIと「AIドリル」を混同しないようにしてほしい、ということです。1人1台端末で「AIドリル」と呼ばれるものに子供が取り組む場合、eラーニングシステムを使っています。これは学習用に考えられたものであり、そのシステムの裏でAIが使われていて、それにより個別最適化ができるわけです。学習用のeラーニングシステムを使えば、その子供がどこまで進んだかが分かります。生成AIと対話をして答えを教えてもらうのとは明らかに違いますから、それを使って学習するのは問題ないと思います。
小学生のうちに身に付けておきたい力とは?
子供たちは13歳になると生成AIが利用可能となるわけですが、その前に、小学生のうちに身に付けておいたほうがいい力があります。それは、文章を書く力と、読んで理解する力です。なぜかというと、適切なプロンプトが書けなければ、求める答えが得られないからです。生成AIに聞けば、プロンプトの内容を教えてもらえますが、それを理解できなければ使いようがなく、対話を続けていけなくなります。
だからといって、特に新しい科目を学ぶ必要はないと思います。小学校でこれまで行ってきた教科の授業の中で、読む、書く、論理的思考などを学習するときに、生成AIの存在を意識してもらえれば、それで十分です。
現在のAIは完成しているわけではない
ここからは未来の話をしたいと思います。今のAIは完成しているわけではないのです。これからもどんどん進化し、高い自律性を持ち、個人に適応していく方向に向かっていきます。人間とAIがセットで「一人の人間」になる、そんな世界になる可能性だってあります。
AIがユーザーのことを完璧に分かってくれて、ユーザーが何をしたいかを理解して先回りして全部やってくれて、しかも完璧な仕事をしてくれるとしたら……人間には空き時間ができるでしょう。その時間に、私なら別の創造的なことをすると思います。AIがどんどん進化し、それをうまく使いこなせれば、新たな価値を生み出せる人が増える可能性があります。
その一方で、生成AIに依存し、自分で考えずに楽をする方向に進み、一つの歯車になる人も出てくるかもしれません。そして、そういう人たちが増えたほうが、都合がいいと考える人たちもいるでしょう。例えば、国民がAIを駆使し、皆が今まで以上に自分でしっかり考えて行動するようになったら、おそらく政治はやりにくくなるでしょう。物事をあまり深く考えずに、人気投票のような感覚で投票してくれる人々のほうが統治しやすいと考える政治家もいるかもしれません。
民主主義の定義からすると、選挙では一人一人がこの国の未来について、目先のことだけではなく長いスパンで考えて投票することが大前提のはずです。それができる人を増やしていかなければ、この国の未来は危うくなります。
皆さんは子供たちにどちらの未来を選んでほしいですか?
今、先生という仕事が重要である理由
この国の未来について考えたとき、小学校の先生の仕事はとても重要になってくると思います。小学生のうちに生成AIに頼らず、自分で考えることの重要性を教えることができるのは先生だけだからです。
だからこそ、先生自身がまず、ゆとりを持ってもらいたいです。事務作業などは生成AIを使って、もっと効率化してはどうでしょう。例えば、通知表の所見欄を書くときは、普段、それぞれの子供の良かった点などをメモしておられると思いますので、そのメモを生成AIに読み込ませて、文章にしてもらうのです。
あるいは、先生の相談役として生成AIを使うのも有効だと思います。子供の思考力を育む授業をどうやって行うかを、生成AIに相談してみてもいいのではないでしょうか。
もちろん、生成AIを有効活用できるかどうかは、校長先生の考え方次第でしょう。今後、全国の小学校で生成AIを使った授業が行われることと思いますが、その鍵を握るのは校長先生です。今まで述べてきたような、生成AIのメリットやデメリットをご理解いただき、学校として活用の方針を示し、子供の思考力を育むような授業をしてもらえればと思います。
技術はどんどん変わっています。1年前と今では、まるで違うものになっています。生成AIは今後、もっと人間対人間のコミュニケーションに近いものになっていくのではないかと思います。
例えば、自分のドラえもんが持てて、普通に対話ができるようになるかもしれません。
ドラえもんはのび太くんが間違ったことをすると、諭してくれます。ですから、将来、ドラえもんレベルのAIができれば、「これを教えるとユーザーが楽をするだけで、本人のためにならないから教えてやらない」などと、考えて行動するようになるかもしれません。
おそらくそこまで行くには、あと5年や10年はかかるでしょう。のび太くんとドラえもんは1対1ですが、今の教室では、先生1人に対して子供が約30人でしょうか。先生方は大変ですが、一人一人の子供をよく見て、今はドラえもんの役も先生がしないといけない、ということです。先生方には頑張っていただきたいと心から思っています。
(取材・構成・文/林 孝美)
関連記事:
https://www.dosokai.st.keio.ac.jp/info/2023rengomitakai/